カーテン色の選び方完全ガイド|部屋別・人気色・プロの提案も
- インテリアウィンドウ
- 8月25日
- 読了時間: 20分

▶︎1. カーテンの色選び方の基本|失敗しないための第一歩

1.1 カーテンの色が部屋に与える印象と心理的な効果
カーテンの色は、部屋の印象を大きく左右します。色によって広く見えたり、落ち着いた空間に感じたりと、想像以上に心理的な影響があるんです。
カーテンの色選び方を間違えると、部屋全体の雰囲気がちぐはぐになってしまいます。
たとえば、こんな心理的効果があることをご存じですか?
ブルー系:気持ちを落ち着かせ、集中力を高める
グリーン系:目にやさしく、リラックス感を与える
イエロー系:気分を明るくし、空間を広く見せる
グレー系:上品で洗練された印象をつくる
忙しい毎日、家に帰ってホッとしたいとき、カーテンの色が気分に合っていると一層リラックスできますよね。
よくある失敗例とその対策
カーテンの色選びでありがちな失敗には、こんなものがあります。
壁紙や家具と合っていない →対策:床・壁・家具の色味を確認して、同系色や中間トーンで揃えると統一感が出ます。
思っていたよりも暗い・重たい印象になった →対策:日当たりが良くない部屋では、白やベージュなどの明るめカラーを選ぶのがポイント。
心理的に落ち着かない色を選んでしまった →対策:寝室は寒色系、リビングは中間色、子ども部屋は明るく楽しい色など、部屋の用途に合わせた色選びを意識しましょう。
生活のシーンに合わせた色選びを
たとえば、在宅ワークが多い方は、集中できるブルーグレーやグリーンのカーテンがおすすめです。
一方で、リビングでは家族全員が心地よく過ごせるよう、柔らかいベージュ系やグレージュが人気。
特に最近では、グレージュやモカベージュといった「中間色」が人気で、落ち着いた雰囲気を出しながらも圧迫感を与えにくいというメリットがあります。
カーテンの色は、単なる装飾ではなく、住む人の心にも影響する大事な要素です。
次は、実際にどんなバランスで色を取り入れれば良いか、配色の基本ルールを紹介していきます。
1.2 色選びで押さえたい配色の基本ルール
カーテンの色を選ぶときに、なんとなく好みで選んでいませんか?
それでも良いのですが、全体のバランスを整えるためには「配色の基本ルール」を押さえておくと、失敗をグッと減らせます。
カーテンの色選び方において、配色バランスはとても大事なポイントです。
配色の黄金比「70:25:5」の法則
部屋づくりでは、次のような比率で色を構成するとバランスが取れやすくなります。
ベースカラー(70%) 壁・床・天井など、空間の大部分を占める色。多くの場合は白やアイボリー。
メインカラー(25%) 家具やカーテンなど、部屋の印象を大きく左右する色。 カーテンはここに含まれることが多く、部屋のテーマに合わせて選びます。
アクセントカラー(5%) クッション・雑貨・アートなどに使う差し色。空間を引き締めたり、個性を出したりします。
たとえば、白い壁にナチュラルウッドの床(ベースカラー)+グリーンのカーテン(メインカラー)+ネイビーのクッション(アクセント)という構成だと、すっきりしてまとまりのある印象になります。
よくある失敗例と解決策
カーテンの色を選ぶとき、次のような失敗もよくあります。
ベース・メイン・アクセントの区別がないまま選んでしまう →対策:色の役割を意識して、全体のバランスをチェックしてみましょう。
アクセントカラーを多用して落ち着かない部屋に →対策:アクセントは小物で抑えめに。カーテンはあくまで「主役」になりすぎない色を。
メインカラーが濃すぎて圧迫感が出る →対策:濃い色を使いたい場合は、床や壁を明るく保つことでバランスをとれます。
毎日の生活に寄り添った配色を
たとえば、朝の光を取り入れたい寝室では、白系や淡いブルーのカーテンがぴったり。
逆に、外からの視線を遮りたいリビングでは、ベージュやグレー系の落ち着いた色が選ばれることが多いです。
日々の生活の中で、部屋に入った瞬間に「なんとなく落ち着かない」と感じることがあれば、それは色の配分バランスが原因かもしれません。
次は、色選びでさらに役立つ色相環やトーンの考え方についてご紹介します。
1.3 色相環とトーンを意識したカーテンの色の選び方
カーテンの色選びでは、好きな色を選ぶだけでなく、「色相環(しきそうかん)」や「トーン」の考え方を取り入れることで、より統一感のあるおしゃれな空間をつくることができます。
カーテンの色選び方において、色の組み合わせは「センス」より「ルール」で決まります。
色相環とは?基本をおさえよう
色相環とは、色の並びを円状に配置したもの。 たとえば次のような関係性があります。
類似色(隣り合う色): まとまりやすく、調和がとれる 例:グリーン×イエローグリーン、ブルー×ブルーグリーン
補色(正反対の位置の色): インパクトがあり、アクセントに使える 例:ブルー×オレンジ、グリーン×レッド
トライアド(正三角形の関係): 彩度を落として使うとおしゃれに 例:ブルー×レッド×イエロー
カーテンは面積が大きいため、原色や補色の組み合わせは少し刺激が強め。 落ち着いた配色にしたい場合は類似色+無彩色(白・グレー・ベージュなど)をベースにするのが無難です。
トーンの違いで印象はこんなに変わる
トーンとは、色の「明るさ」や「鮮やかさ」のこと。 同じ色でも、トーンが違うと部屋の印象もガラッと変わります。
ライトトーン(淡い色): 広く見せたい部屋にぴったり
ダークトーン(濃い色): 落ち着いた雰囲気を出したいときに最適
ソフトトーン(くすみ色): ナチュラルな雰囲気で人気
ビビッドトーン(鮮やか): 子ども部屋など楽しい印象に
最近では、「くすみカラー(スモーキートーン)」の人気が高く、特にグレージュやモカ、アースカラー系が好まれています。
よくある失敗とその対策
色相関係を無視して配色がバラバラに →対策:色相環で「隣り合う色」か「無彩色との組み合わせ」かを意識しましょう。
ビビッドな色を選んで目が疲れる部屋に →対策:トーンを落として、ソフト・ダーク・グレイッシュ系にすると◎
部屋全体が暗くなってしまった →対策:カーテンが暗めの色なら、壁・床を明るめにして調整しましょう。
毎日の気分に影響する「色とトーン」
たとえば、くすみブルーのカーテンは目に優しく、朝の光にもなじみやすいので、リビングや寝室でも人気です。
逆に、濃いネイビーを使う場合は、部屋全体のバランスを考えて、家具や床を明るめにするのがポイント。
色とトーンを少し意識するだけで、同じ部屋でも「プロにコーディネートされたような印象」に近づけることができます。
▶︎2. 部屋別カーテンの色選び方|空間に合った配色で失敗しない

2.1 リビングにおすすめのカーテン色選び方
リビングは、家族が集まり来客もある“家の顔”となる空間。
ここでは、清潔感や安心感を与えつつ、インテリア全体と調和する色が求められます。
リビングのカーテン色選び方では「誰が来ても落ち着ける色」が大事です。
よく使われる色とその理由
グレー・ベージュ系: 空間になじみやすく、家具とも合わせやすい
グレージュ: トレンド感もあり、ナチュラルテイストとの相性も抜群
ネイビー・モカ: 高級感を出したい場合におすすめ
よくある失敗と解決策
色が家具とぶつかって雑多な印象に →対策:ソファやラグなど、大物のカラーと同系色で揃えると統一感アップ
白すぎて落ち着かない →対策:真っ白ではなく、アイボリーやグレーホワイトを選ぶと◎
無難すぎて地味になってしまう →対策:タッセルやレースでアクセントをプラスしておしゃれに演出
生活の中のシーンにあった提案
たとえば休日の昼下がり。 家族で映画を見たり、お客様を迎えたりする時間、カーテンの色ひとつで雰囲気はガラッと変わります。
自然光を活かせる明るめのグレージュやベージュが、リラックスした空間づくりにぴったりです。
2.2 寝室でリラックスできるカーテンの色選び方
寝室では何よりも「心と体を休められる空間づくり」が大切です。 そのためには、色が持つ心理的な作用を上手に活かすことが重要です。
寝室のカーテン色選び方では「安眠できる色」を意識しましょう。
寝室に合う色の特徴
ブルー系(くすみブルー、ネイビー):心拍数を落ち着かせる
グリーン系(オリーブ、モスグリーン):目に優しく疲れを癒す
グレージュやチャコールグレー:光をやわらかく抑える効果が◎
よくある失敗と解決策
白系で眩しすぎて睡眠を妨げる →対策:遮光性能を確認しつつ、くすみカラーや中間色に変更
原色に近い鮮やかな色を選んでしまい、落ち着かない →対策:トーンを落として、スモーキー系・ソフトトーンで統一
日差しを遮りすぎて朝が暗い →対策:レースカーテンと組み合わせて、調整できる仕様にする
安らぎの空間に変わる配色のコツ
たとえば仕事終わりの夜、ブルーグレーのカーテンが閉じられた空間で、ほのかに漏れる間接照明…。
そんなシーンを演出できれば、寝る前の時間がより贅沢になります。
落ち着いたトーンのカーテンは、照明や寝具とも自然に調和します。
2.3 書斎・子ども部屋・ワンルーム別のカーテン色選び方
それぞれの空間に求められる役割は違うため、カーテンの色にもメリハリをつける必要があります。
目的に合わせた配色がポイントです。
書斎・ワークスペース
ブルーグレーやチャコール系: 集中力アップ+光の反射を抑える
ライトグレーや生成り: 自然光を活かして明るさもキープ
色選びのポイントは「集中を邪魔しない落ち着いた色」です。
子ども部屋
パステルカラー(ピンク・イエロー・ミントなど): 明るく楽しい印象に
くすみトーンのブルーやラベンダー: 成長に合わせて長く使えるデザインも◎
注意点として、ビビッドカラーは刺激が強いため、壁・床とのバランスを考慮して選びましょう。
ワンルーム
ベージュやアイボリー: 空間を広く見せる定番カラー
グレージュやモカブラウン: インテリア全体と馴染みやすく、生活感を隠せる
収納の少ないワンルームでは、カーテンで部屋全体の印象を整える役割も重要。 くすみ系の中間色がとても重宝されています。
生活シーンにあわせた色の選び方が成功のカギ
一人暮らしでもファミリーでも、「カーテンの色」は生活の質に直結します。 特に空間が限られる家では、1色の選び方が空間全体の印象を左右することも多いです。
部屋ごとの目的と生活動線に合わせた色選びが、快適な空間づくりの第一歩です。
▶︎3. 人気カラー別に見るカーテンの色選び方|失敗しない傾向と対策

3.1 定番色で安定感を出すカーテンの色選び方
カーテンの色選びでまず候補に上がるのが「定番カラー」です。
どんなインテリアにも合わせやすく、安心感があるため人気が高いです。
定番色は「飽きずに長く使える」のが最大の魅力です。
よく使われる定番色と特徴
グレー系: スタイリッシュで空間に奥行きを与える
ホワイト系(アイボリー含む): 明るく開放感があり、清潔感も◎
ベージュ系: 柔らかくナチュラルな印象に
よくある失敗と解決策
白すぎて病院のような印象に →対策:アイボリーや生成りなど、少しトーンを落とすと自然な雰囲気に
グレーが寒々しく感じる →対策:あたたかみのあるライトグレーやグレージュに変更
ベージュが古臭く感じる →対策:モカやサンドベージュなど、くすみ系のトーンにすると今っぽさが出ます
安定した空間を演出するには
忙しい朝や疲れて帰宅したとき、空間に「落ち着き」を感じるだけで気持ちがラクになりますよね。
そんな安心感を与えてくれるのが、これらの定番色です。
とくにホワイト系+ウッド素材の家具の組み合わせは、温かみと清潔感を両立できます。
3.2 トレンドカラーを取り入れたカーテン色選び方
最近ではSNSや雑誌でも「トレンドカラー」を取り入れたカーテンが注目されています。
一気におしゃれな印象に仕上がる反面、選び方を間違えると浮いてしまうことも。
トレンドカラーは「さりげなく取り入れる」のがコツです。
注目されているカラーと特徴
グレージュ: グレーとベージュの中間で使いやすく大人気
アースカラー(オリーブ・テラコッタ・モカなど): 自然な色味で空間になじむ
くすみ系グリーン・ブルー・ラベンダー: 女性にも人気の柔らかカラー
よくある失敗と解決策
壁や床と合わず浮いてしまう →対策:インテリア全体のトーンを統一し、同系色の小物を使う
流行が過ぎて古く感じるように →対策:ベースカラーは定番、トレンド色はレースやアクセントで取り入れる
気に入って買ったが落ち着かない →対策:くすみカラーに変更すると、視覚的にやさしく感じられる
上手にトレンドを取り入れるテクニック
たとえばグレージュのカーテンに、グリーン系の植物や木目家具を合わせると、統一感のある“今っぽい空間”になります。
1〜2年で変えたくなる人には、トレンド色をレースカーテンやタッセルで取り入れるのもおすすめです。
3.3 色が持つ印象と空間との相性を考えた選び方
カーテンは色そのものだけでなく、「空間に与える印象」まで考えて選ぶと、より効果的に活用できます。
色にはそれぞれ“空間を変える力”があります。
主な色と与える印象
色の系統 | 印象・心理効果 | 向いている空間 |
ブルー系 | 落ち着き・冷静・清潔感 | 寝室・書斎 |
グリーン系 | 安心感・癒し・自然 | リビング・子ども部屋 |
ベージュ系 | 柔らかさ・ナチュラル | リビング・ダイニング |
グレー系 | 洗練・静けさ・都会的 | ワンルーム・書斎 |
イエロー系 | 明るさ・陽気さ・活発 | 子ども部屋・キッチン |
パープル系 | 上品さ・ミステリアス・個性 | 寝室・趣味部屋など |
よくあるミスマッチの失敗と対策
落ち着きたい空間に刺激の強い色を選んでしまう →対策:目的に応じた色の心理効果を把握しよう
同じ色でもトーンが部屋に合わない →対策:部屋の明るさや面積に応じてトーンを調整する
印象にばらつきが出てインテリアが散漫に →対策:家具・床・壁の色をベースに、統一感ある色選びを
色の効果を活かしたコーディネート例
たとえば、ネイビーのカーテンを使った寝室は、重厚感がありながらも深いリラックス感が得られます。 一方で、グリーン系のカーテンを取り入れたリビングでは、植物や木製家具との相性がよく、自然な雰囲気に仕上がります。
目的に合わせた色選びが、空間の印象をガラッと変えてくれます。
▶︎4. カーテンの色選び方でありがちな失敗とその解決法
4.1 部屋が狭く見えるカーテン色の失敗例と対策
カーテンの色は、部屋の広さの印象にも影響します。
知らずに選んでしまうと「なんだか圧迫感がある…」という仕上がりになることも。
カーテンの色選び方でよくある失敗が「部屋が狭く感じる」ことです。
よくある失敗パターン
暗すぎる色を選んでしまい圧迫感が出る →対策:明るいトーンのベージュやライトグレーで空間に余白感を
カーテンの色だけが浮いて壁との統一感がない →対策:壁の色に近い無彩色(グレー・ホワイト系)でなじませる
丈やサイズが合っておらず、視覚的に狭く見える →対策:天井から床までの長さでフル丈カーテンにすると縦の広がりが生まれる
圧迫感を避けたいときのポイント
たとえば6畳ほどのコンパクトな部屋でネイビーの厚手カーテンを使うと、どうしても重く見えがちです。 その場合、アイボリーの遮光カーテンに替えるだけで、「一気に広く明るく見える」ようになります。
4.2 カーテンだけ浮く・ちぐはぐになる配色のNGパターン
おしゃれにしたくて選んだカーテンでも、他のインテリアと合わなければ、かえって統一感が崩れてしまいます。
カーテンの色選び方で失敗しやすいのが「色だけが浮いてしまう」ケースです。
よくあるちぐはぐ配色の原因
インテリアテーマを無視して好きな色を選ぶ →対策:家具やラグなど、空間の「主役」になるアイテムとの相性を見てから決める
アクセントカラーを複数入れすぎて散漫になる →対策:メイン+1色のアクセントに絞ってバランスを整える
レースとドレープの色が合っていない →対策:同系色またはグラデーションになるような組み合わせにする
統一感を出すために意識したいこと
たとえば、木目のナチュラル家具が多い部屋に、原色系のカーテンを合わせてしまうとかなり違和感があります。
この場合はベージュやグレージュを選ぶことで、全体に温かみとまとまりが生まれます。
「目立たせたいのはどこか?」を考えることで、カーテンの役割もはっきりしてきます。
4.3 色と素材の機能面を見落とした後悔と解消法
色だけに注目してしまいがちですが、実は素材感や機能も大きな影響を与えます。特に「遮光性」や「透け感」を無視して選ぶと、生活の快適さに直結する後悔が起こりやすいです。
カーテンの色選び方では、素材や機能との“相性”が意外と重要なんです。
よくある後悔とその理由
遮光カーテンなのに圧迫感が強すぎた →対策:ダークカラーを避け、グレー系の遮光生地で明るさと遮光を両立
レースカーテンが透けすぎてプライバシーが気になる →対策:ミラーレースや目が細かい素材を選ぶ
素材の質感が部屋の雰囲気に合わない →対策:ナチュラルな空間にはリネン風や綿素材、モダン空間にはシャープなポリエステルなどを選ぶと統一感が出る
生活スタイルに合った機能を選ぶコツ
たとえば、朝日がよく入る寝室に遮光性の低い淡色カーテンを選んでしまうと、睡眠の質が落ちてしまうことも。 一方、遮光1級のグレー系カーテンを使えば、朝までぐっすり快眠できる環境になります。
色と素材を一緒に考えることで、デザイン性だけでなく「快適さ」も手に入れられます。
▶︎5. プロが提案するカーテンの色選び方|オーダー対応で理想を実現
5.1 サンプル活用で安心!失敗しないカーテン色選び方
カーテンの色は写真で見るのと、実際の部屋で見るのとでは印象がまったく違います。
だからこそ、購入前に「サンプル」を取り寄せるのがおすすめです。
サンプルを活用することで、色の失敗をぐっと減らせます。
サンプルを取り寄せるメリット
実際の光の入り方や時間帯で色の見え方を確認できる
家具・床との相性をその場で比較できる
生地の質感や透け具合も触ってチェックできる
よくある「画像だけで選んで失敗した例」
想像より色が濃かった/薄かった
→対策:昼と夜、照明下でも色の変化を見ておく
手持ちの家具と微妙にトーンがズレてちぐはぐに →対策:壁紙や床との色も一緒に並べて確認する
透け感がイメージと違ってプライバシーが気になる →対策:レースとドレープ両方のサンプルを取り寄せて判断する
サンプル活用の流れ(御社サービスの場合)
御社では、オーダーカーテン4000品目以上の中から、気になる生地のサンプルを無料(一部有料)で請求可能。 手元に届いたサンプルを、部屋の壁や窓に当てながら比較できるため、自分に合った色が見つけやすくなります。
5.2 高品質・低価格を両立したインテリアウィンドウサービスの強み
色選びに失敗したくない人にとって、選択肢が豊富で価格が明確なサービスは心強い存在です。
インテリアウィンドウでは「業界最安値2980円〜」という価格帯で、プロ仕様のオーダーカーテンを提供しています。
主なサービスの魅力
オーダーメイド4000品目以上から選べる
カーテンレールからブラインドまで幅広く対応
カーテンレール取り付け2980円~の低価格
最短即日で設置できるスピード対応(※地域限定)
よくある購入時の不安もサポート
採寸の仕方がわからない →対策:オンラインでの採寸ガイドや、スタッフによるサポートあり
取り付けができるか不安 →対策:プロによる取り付け工事も対応しており、初心者でも安心
どの色を選べば良いかわからない →対策:無料相談や施工事例の紹介が豊富なので、イメージしやすい
コストを抑えながら理想の空間を実現
たとえば、同じグレージュのカーテンでも、素材や遮光性で価格が異なることがあります。 インテリアウィンドウでは、希望の予算や用途に応じて選べるので、「高見えするカーテンを安く導入」することも可能です。
5.3 初めてでも安心!設置・見積もりサポートの活用法
カーテン選びが初めての方にとって、「何を基準に選べばいいのかわからない」「失敗しそうで不安」と感じることはよくあります。
そんなときに頼りになるのが、インテリアウィンドウの丁寧なサポート体制です。
サポート内容一覧
無料見積もりサービス(一部有料オプションあり)
電話・メールでの相談対応
最短即日での施工サービス(エリア限定)
初心者に多いお悩みと対策
窓のサイズを間違えて注文しそう →対策:サイズの測り方マニュアルを活用+不明点は問い合わせ可能
自分の部屋にどの色が合うか判断できない →対策:実例集やサンプルを見ながら相談できるサービスが安心
取付方法がわからずDIYを諦めたくなる →対策:取付込みのセット価格もあり、施工までまるっと任せられる
忙しい方でも手軽に頼める仕組み
たとえば、平日は仕事で時間が取れない方でも、事前のメール相談と日時予約でスムーズに設置まで完了します。
価格・品質・スピード感のバランスが整っているのが、インテリアウィンドウの大きな魅力です。
▶︎6. カーテンの色の選び方まとめ|空間に合う色選びのコツとご案内
6.1 今回の記事のふりかえりとポイント整理
ここまで「カーテンの色の選び方」について、空間別・色別・失敗例と対策・プロのサポート活用まで幅広くご紹介してきました。
まず押さえておきたいのは、カーテンの色は見た目だけでなく、心地よさや過ごしやすさに大きく関わるということです。
この記事でご紹介した主なポイント
部屋別(リビング・寝室・書斎など)に最適な色の特徴と選び方
色相環・トーン・配色比率など、基本的なカラーコーディネートの知識
よくある失敗(圧迫感、色のミスマッチ、素材選び)とその対策
プロによるサンプル提供・見積もり・施工サポートの有効な使い方
「なんとなく」で選ばずに、色の持つ印象や空間との相性を意識することで、後悔しないカーテン選びが実現できます。
6.2 カーテンの色選び方で後悔しないための3つの工夫
カーテンは大きな面積を占めるため、色の選び方ひとつで空間の雰囲気が大きく変わります。
後悔しないためには、次の3つを意識することが大切です。
① 実際の部屋で色を確認する
サンプルを取り寄せて、自然光・照明下での色の見え方を比較しましょう
家具や床とのバランスをその場で確認できるのが大きなポイントです
② 部屋の目的に合わせて色を選ぶ
寝室には落ち着いたトーン、リビングには調和しやすい中間色など
心理的な影響も考慮すると、暮らしの質もアップします
③ プロのサービスを活用する
採寸・設置・コーディネートまで一貫してサポートしてくれるプロに頼ると安心
特に初めての方や失敗経験がある方には心強い味方になります
たった3つの工夫で、満足度の高いカーテン選びがグッと近づきます。
6.3 インテリアウィンドウのサービスで理想の窓辺を実現しよう
もし「どの色が合うかわからない」「サイズの測り方に不安がある」「プロに任せて安心したい」と感じたら、インテリアウィンドウのサービスを活用するのがおすすめです。
インテリアウィンドウのサービスの特徴まとめ
4000品目以上から選べるオーダーカーテン
カーテンレール・ロールスクリーン・ブラインドまで一括対応
業界最安値2980円〜/無料見積もり/最短即日施工
初めてでも安心の丁寧なサポート体制
たとえば、サンプルを取り寄せて部屋で実物確認 → 無料見積もり → 設置までをワンストップで対応してくれるので、失敗のリスクが大幅に減ります。
カーテン選びで「プロに相談してよかった」と実感できるサービスです。
カーテンの色選びは、暮らしを快適にする第一歩。
納得いく色・素材・デザインを選んで、毎日がもっと心地よくなる空間をつくっていきましょう。
▶︎カーテンの色選びから設置まで、カーテン選びで迷ったらインテリアウィンドウに相談を!
業界最安値2980円〜、最短即日施工可能なインテリアウィンドウのサービスを活用して、快適な窓辺を手に入れましょう。
無料見積もりもあるので、まずはお気軽にお問い合わせください。


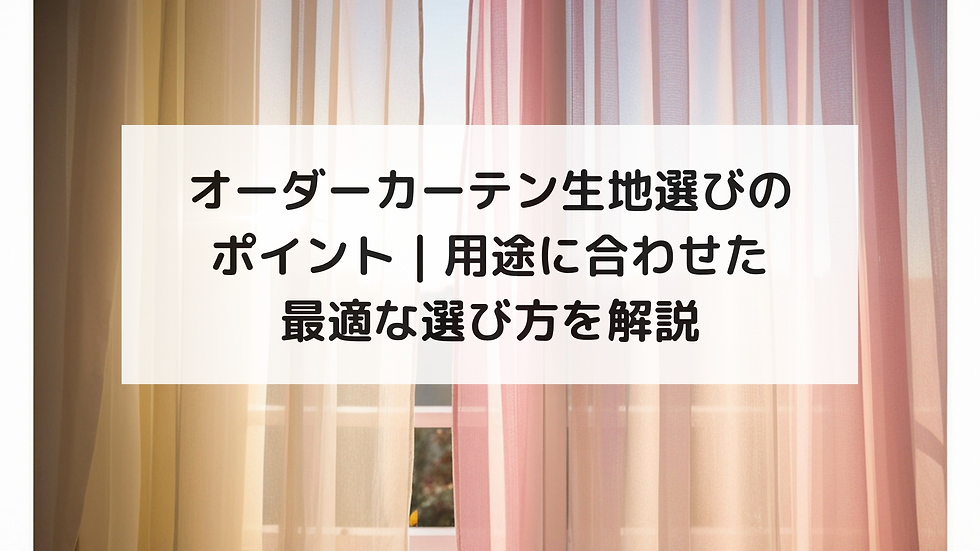

コメント